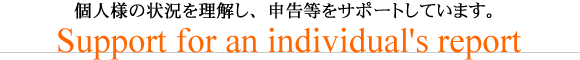
初心者でもわかる!不動産所得の確定申告と節税のやりかたとは
不動産から収入が発生した場合、確定申告が必要です。
今まで全くしたことがない方にとって確定申告は「難しそう」「何から手をつけていいのか分からない」などネガティブなイメージがつきまとっていると思います。
ですが基本的なやりかたを知ってしまえば、自分で確定申告を行うことも可能です。
これから税理士に依頼される予定の方も、自分で確定申告される方も、まずは基本的な知識を身につけ、賢く申告しましょう。
支払う税金を少なくするための節税方法についても解説しています。
ぜひ最後までお読みください。
目次
1.不動産所得とは?

不動産所得とは、マンションや駐車場などの不動産を他人に貸して得られた所得のことをいいます。
-
1-1.「所得」とは
所得とは、「収入-経費」のことを指します。
たとえば、駐車場からの収入が10万円、駐車場の整備などにかかった経費が6万円であれば、
10万円-6万円=4万円
所得は4万円です。
-
1-2.他にも所得の種類があるの?
所得は10種類に分けられており、不動産所得はそのひとつです。
不動産所得の他には下記の9つがあり、それぞれ税金の計算方法が異なります。
もし他にも所得があるのなら、それぞれ分けて計算し、後ほど合算します。
給与所得:サラリーマンの方が会社から受け取った給料など
利子所得:預金の利子や投資信託の分配金など
配当所得:株主に支払われる配当金など
一時所得:生命保険の満期保険金、競馬や競輪の払戻金、懸賞に当たった時の賞金など
山林所得:山林を伐採して譲渡した時の所得など
退職所得:退職金など
譲渡所得:土地や建物、ゴルフ会員権などを売却したときの所得など
雑所得:公的年金など、他の9つの所得のいずれにも当たらない所得
所得は10種類に分けられており、不動産所得はそのひとつです。
-
1-3.副業でも確定申告は必要
基本的には副業であっても確定申告は必須です。
会社で行なっている年末調整は、あくまで「会社からあなたに支払われた給料に対する税金の計算」をしているにすぎません。
不動産所得に関する税金の計算はしてくれませんので自分で行います。
ご注意ください。
2.不動産所得で確定申告が不要なケース

サラリーマンなどの給与収入がある人:副業かつ不動産所得が年間20万円以下
自営業の人:副業かつ不動産所得が年間48万円以下
この範囲であれば確定申告は必要ないと定められています。
とはいえ、不動産所得は金額が大きくなるものですから、
年間所得が20万円もしくは48万円以下におさまることは極めて稀です。
基本的に不動産所得が発生したら確定申告が必要だと覚えておいてください。
ご相談などのお問い合わせはこちらまで
(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)
※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。
3.不動産所得の確定申告で注意すべきこと

-
3-1.親族に無料で貸した場合は不利になる
子ども夫婦や両親には、無料で部屋や駐車場を貸し出すことが多いようです。
この場合、無料で貸し出した土地建物の部分について、減価償却費や固定資産税などの経費が認められません。
たとえば5部屋所有しているうちの1部屋を親族に無料で貸している場合、単純計算で減価償却費と固定資産税の1/5が費用計上できなくなります。さらに相続税や贈与税でも不利になります。
では1円以上の賃料をもらっていれば問題ないのかというと、そうでもありません。
固定資産税や不動産の維持にかかる経費を下回る賃料ですと、「不動産所得を得るために不動産を貸し出した」とはいえず、親族に貸し出した不動産にかかる経費は認められません。
詳細は税理士へご相談ください。
-
3-2.土地や駐車場の場合は計算方法が異なる
土地や駐車場の経営をしている場合は、運営形態や事業規模によって不動産所得・事業所得・雑所得のいずれかになります。
所得の計算方法が若干異なりますので、確定申告に手をつける前に調べておきましょう。
■不動産所得になるケース
他人に車を停めるスペースを提供しているだけで、盗難トラブルなどの責任を負わないケースです。
駐車場に「トラブルには一切責任を負いません」という看板があれば、そこは不動産所得で計上している駐車場です。
■事業所得になるケース
駐車場内のトラブルにも責任を負い、事業規模が比較的大きい場合には事業所得に分類されます。
一般的には、出入り口を管理し、数十台以上を管理運営している駐車場です。
■雑所得になるケース
駐車場内を管理しているのは事業所得と同じですが、運営規模が小さい場合は雑所得になります。
4.不動産所得の計算方法

基本的な計算方法は以下のとおりです。
不動産から得られた収入合計-必要経費=不動産所得金額
この式を作成するために、3つのステップを踏んでいきます。
-
4-1.不動産から得られた年間収入を計算する
1月1日〜12月31日までに得られた不動産収入を足します。
見込みではなく、実際に支払われた金額の合計を計算してください。
支払いが遅れて年内に間に合わなかった場合は、翌年の収入にするのが一般的です。
-
4-2.必要経費を計算する
不動産にかかった必要経費を計算します。
年間で使用した経費は膨大でしょうから、レシートや振込票などを手元に並べて、ひとつずつ確認しながら一旦書き出すことをお勧めします。
減価償却費も忘れずに計算しましょう。
経費にできるものとできないものについては下記で詳しく説明していますので、一度お目通しください。
-
4-3.年間収入から必要経費を差し引く
収入-経費を計算します。
これで不動産所得は算出できました。
ご相談などのお問い合わせはこちらまで
(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)
※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。
5.不動産所得の確定申告の方法

1 書類の準備
確定申告を始める前に、必要書類を準備しておきましょう。
不動産売買契約書や借主との賃貸借契約書、管理費の控えなどです。
他に収入がある場合は、その書類も不動産所得とは別にまとめておきましょう。
2 決算書もしくは収支内訳書の作成
青色申告の届出を税務署に提出している場合は決算書を、提出していない場合は収支内訳書を作成します。
決算書と収支内訳書はどちらも不動産の収入と経費を明記する書類です。
決算書の記載方法は複式簿記といい、収支内訳書の単式簿記よりも複雑です。
ただしそのぶん最大65万円を所得から差し引けます。
つまり節税になるということです。不動産所得の場合、65万円の控除を受けられる人は10室以上の不動産を持っているなど、限られていますので、詳しくは税理士に尋ねてください。
3 確定申告書の作成
確定申告書Bという様式に、決算書もしくは収支内訳書で計算した金額を記載します。
また別の収入がある場合や医療費控除や保険料控除を受ける場合もこちらに記入します。
年末調整済みの給与所得も確定申告書に記入してください。
確定申告書は各税務署に備え付けてある書類に書き入れるか、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用してください。
4 確定申告
申告方法は
・税務署の窓口に直接提出
・税務署に郵送
・ネット上で電子申告
の3パターンが選べます。
2020年10月現在では、電子申告を行うのにICカードと専用のカードリーダが必要です。
申告が終わりましたら、引き落としや現金などで税金を支払いましょう。
6.不動産所得での節税方法

-
6-1.経費を積み上げる
不動産所得は他の所得と比べて経費計上できる項目が少ないのが難点です。
減価償却費しか費用計上していないと所得額が膨れてしまい、必要以上に税金を支払っている方も見受けられます。
経費にできるものをチェックして、できる限り計上しましょう。
■経費にできるもの
・不動産購入にかかるローンの金利
・不動産の修理やリフォーム費用
・不動産にかけた火災保険や地震保険など
・不動産の共有部分の電気代
・管理会社への管理委託料や管理費
・仲介手数料や広告にかかった費用
・固定資産税などの税金関係(一部経費計上不可。下記参照)
・司法書士や税理士へ支払った報酬
・電話代やWi-Fi代
・交通費や宿泊費
・車の購入費用やメンテナンス費用
・新聞代やセミナー参加費用
・飲食代
・減価償却費
■経費にできないもの
・不動産購入や設備維持などに関係のない支出全般
・スーツやクツ、腕時計など身につけるもの
・ジムや習い事などの会費
・反則金や罰金
・所得税、住民税、法人税
あくまで経費にできるものは「不動産購入や設備維持などに必要な費用」に限られます。
私用で使った運賃や友人と飲食した場合のお金などは、不動産所得の経費とは認められません。
-
6-2.減価償却費を活用する
減価償却とは、土地以外の資産価値の減少分を必要経費にした経費のことです。
たとえば屋根や雨樋、ドアなどは、使用年数とともに古くなり価値が下がってきますよね。
この目減りした資産価値を減価償却費として計上できます。
減価償却費は非常に高額ですので、最大化できるように工夫しましょう。
具体的にはできるだけ「建物」と「付属設備」を区分することです。
建物」の償却期間は22〜47年とかなり長期になるため、そのぶん1年単位で計上できる費用は少なくなります。
一方で「付属設備」の減価償却期間は15年がほとんどです。
償却期間が圧縮されるので、それだけ年間の費用計上可能額が増加します。
もちろん償却期間が終われば、その後は減価償却費を計上できません。
ただしそのタイミングで売却し他の不動産を手に入れれば、問題なく運用できます。
-
6-3.赤字になっても確定申告を行う
不動産所得の確定申告を行うと「損益通算」ができます。
損益通算とは、赤字になった所得を黒字の所得から差し引いて税金の金額を計算できる制度です。
不動産を購入した初年度は特に購入にかかる費用が膨らみ、赤字になるリスクが大きいものです。
給与所得や年金など他の収入があるようでしたら、不動産所得が赤字でも確定申告を行い、他の所得にかかる税金を少しでも減らしましょう。
-
6-4.法人化する
ある程度不動産所得が増えてきたら、法人化して所得税や相続税を安く抑える選択も考えられます。
法人化するとかかる税金が所得税から法人税と名前を変え、税金の計算方法も変わってくるからです。
また、家族を役員にして役員報酬を支払えば、経費が増えてさらに節税効果が高まります。
法人化を検討される場合は、税理士にご相談ください。
7.まとめ
不動産所得が20万円以上発生したら、副業でも確定申告が必要です。
難しそうなイメージがありますが、一度理解してしまえば個人でも確定申告はできます。
ただし経費計上できる範囲や節税対策を行うとなると、個人で対応しきれない部分も出てくるでしょう。
専門家に依頼すれば、あなたの支払う税金が最小限に抑えられます。
不動産の確定申告については、信頼できる税理士にお早めにご相談ください。
畑会計事務所では、このような確定申告に関する疑問等に対し、サポートを行っております。
関連記事